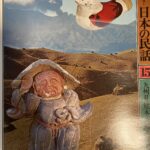はじめに
皆さん今日は、たまなぎこと珠下(たまもと)なぎです。
今日も来て下さって、ありがとうございます!
今日は高千穂旅行記2回目。槵觸(くしふる)神社、荒立神社、天の真名井です。
1回目、高千穂神社の記事をご覧になりたい方はこちら↓
槵觸(くしふる)神社
槵觸神社は、高千穂神社から車で3分ほど。
天孫瓊瓊杵尊が最初に降り立ったのが「筑紫の日向の高千穂のくしふる岳」。
つまり、天孫降臨神話の始まりの地です。

かつては山自体をご神体としていましたが、元禄時代に社殿が建てられたそうです。
日本の神社は、記紀の編纂後、それぞれの神々の性格が定められた後、ご利益目当てに社殿を建ててその神に来ていただく(勧請)、という形が多いのですが、ここは、社殿が建てられる前から信仰があり、その後社殿が建てられたという由緒正しい神社。たまなぎ的には一番そそるタイプの神社です。
しかし、山自体がご神体だったというだけあって、社殿が遠い! いや、高い!

なかなかの運動量でした(笑)。
参道は見事にまっすぐ……それはそう、皇室の祖先神ですからね。
参道の周りには立派な木々が生い茂り、直射日光を和らげてくれます。まるで天然のエアコン。
人も少なく、清浄な気に満たされた神社でした。
相撲の奉納も行われているそうで、土俵もありました。
ここは武甕槌命(出雲で大国主に国譲りを迫った神)を祀っており、武甕槌命と健御名方神(大国主の子)の勝負を相撲の起源と考えて相撲を奉納しているそうです(一般的には相撲の起源は野見宿禰と当麻蹴速の勝負と言われています)。
天の真名井
こちらは神社ではありませんが、天孫がこの地に降り立った時、水がなかったため天村雲命が水種を移されたと伝えられているそうです。
いやいや、そんなわけないだろと突っ込みたくなりましたが……。
猿田彦や大山津見神など、ここには既に先住者がいたのですが、水がなかったわけがなかろう……と思うのですが、伝説がそうなっていますので仕方ない。

上から写したところ。黒っぽく見えるのは底の石が黒いせい。飲み水ではありませんでしたが、水は澄んでいて冷たかったです。

ここを水源とする滝を、高千穂峡で「真名井の滝」として見ることがでます。
荒立神社
こちらもちょっと面白い神社です。
御祭神は猿田彦なのですが、地元の作家高山文彦氏の著書『鬼降る森』によると、荒立神社の宮司を代々務めた興梠氏は、もともと「神呂木」と表記したそうです。そして、「神呂木」は鬼八に捧げる木を指したと。そしてこの興梠氏こそが、鬼八の物語を現代に語りついだのではと推論されています。詳しくは↓
さて、この荒立神社。天鈿女命(あめのうずめのみこと)と猿田彦が結婚して移り住んだ地とされます。天鈿女命は、天照大神が素戔嗚尊の乱暴に怒って天岩戸に隠れてしまった時、踊りを踊って天照大神の関心を引き、天照大神を引っ張り出す作戦を成功させた神。
ですから、この神社は芸能と縁結びのご利益があると言われています。
あちこちに、「7回打つと7つの願い事がかなう」という板が置かれていました。
ハートをかたどったユニークな板も。

この3か所は駐車場もあり、さくさくと回ることが出来ました。
この後、本日の最終目的地である天岩戸神社に向かいました。
さいごに
高千穂は天孫降臨神話の地だけあり、古代の歴史がそのまま現代に伝えられています。
古代史好きにとっては回りがいのある場所でした。
高千穂町の公式ページにも色々情報が載っていますので、興味ある方はご参照ください。
高千穂町観光協会【公式】 宮崎県 高千穂の観光・宿泊・イベント情報
最後までお読みいただき、ありがとうございました!